戦国時代――それは、わずかな油断が命取りとなり、昨日までの味方が明日には敵になる、まさに弱肉強食の世界でした。
人の命が紙よりも軽かったこの時代、生き延びることそのものが戦いだったのです。
そんな苛烈な時代を生き抜いた武士や大名たちは、勝つため、守るため、名を残すために、ときに非情な手段を選びました。
その中には、現代の価値観では到底理解しがたい「残酷な習慣」も多く存在していました。
もちろん、そこには乱暴な野蛮さだけでなく、宗教的な信仰や政治的合理性、時には“人間らしさ”さえ見え隠れします。
しかし、何より恐ろしいのは――それらが当時では“普通”だったという事実です。
今回は、戦国の世に実際に行われていた**「残酷な習慣」6つ**を紹介します。
戦国時代の真の姿を知ることで、現代の「平和」や「命の価値」を改めて見つめ直すきっかけになれば幸いです。
目次
現代では考えられない、戦国のリアル6選
首実検(くびじっけん)

「首実検」とは、読んで字のごとく「その首が本物かどうかを検(あらた)める」ための儀式です。
戦場で討ち取った相手が名のある武将であれば、その首級を持ち帰り、上官が顔を確認し戦功として評価します。
しかし、単なる確認で終わるわけではありません。
**討ち取られた者の怨霊に祟られぬよう、塩で清めたり香を焚いたりする「鎮魂の儀式」**もセットで行われていました。
首実験の話で有名なのが、織田信長による残虐な振る舞いでしょう。
敵の首を足蹴にする、罵声を浴びせるといった行為は、まさに“力による支配”の象徴でもありました。
また、首実検は焼死体や損傷の激しい遺体には適用できないため、確認が困難になります。
本能寺の変で焼け死んだとされる信長の遺体が見つからなかったのも、信長が焼けてしまったことによって、顔の判別ができなくなったことが原因であるとも言われています。
家族ごと処刑 一族皆殺しの非情な制裁
戦国時代の「忠義」とは、裏切りを許さないことを意味しました。
一度でも謀反を起こせば、本人だけでなく、その家族・親戚・家臣にまで処刑の刃が及ぶことも珍しくありませんでした。
「仇討ち」を恐れた結果、赤子や女子供まで容赦されなかったのです。
有名な例として、松永久秀や明智光秀の一族処刑が挙げられます。
彼らの謀反により、家族や関係者も多くが命を落としました。
これは、忠誠を裏切ることが「血縁の断絶」という最終的な罰とセットだったことを物語っています。
落城時の集団自害 ― 武士と女性たちの選んだ最期
戦国の城において、落城はすなわち「死」を意味しました。
城主や武士たちは潔く切腹し、女性たちも敵兵の辱めを受けるくらいならと自害を選ぶことがありました。
特に名家の姫や奥女中たちは、短刀で喉を突く・井戸に身を投げる・火を放って炎に身を包ませるなど、壮絶な最期を遂げた記録も残っています。
例として有名なのが、山中鹿之助の妻の最期や、信長の次男・信雄の家臣団の自害など。
こうした行動は「家名を守るため」「敵に辱めを受けるよりは武士らしく死ぬ」という価値観に支えられていました。
人柱
城や橋などの大規模建築では、霊を鎮めるために人柱を立てるという信仰が存在しました。
これは「工事の無事」と「建造物の安定」を祈るもので、時に罪人や若い娘が生きたまま土中に埋められたとされます。
記録として有名なのが、丸岡城の人柱伝説。
足場が崩れてばかりだった石垣工事の際、一人の女性が犠牲となり、以後は安定したという逸話が残っています。
もちろんすべてが史実というわけではありませんが、当時の人々が命と引き換えに「建物の加護」を求めていたことは事実です。
人質外交 ― 子どもたちが交渉材料になる時代

戦国大名の間では、同盟を結ぶ際に子どもや妻を人質として差し出すことが常でした。
これは単なる「担保」ではなく、裏切りがあれば即座に処刑される可能性のある命がけの交渉手段だったのです。
幼い頃の徳川家康(当時の竹千代)も、今川義元への人質として送られました。
人質先では丁重に扱われることもあれば、監視や脅迫の対象になることもありました。
また、人質同士が育む友情や恋愛が、後の政略結婚や裏切りにつながることもあったため、人質制度は単なる人間の貸し借りにとどまらない政治装置でもあったのです。
耳塚(鼻塚) ― 首の代わりに切り取られた「証拠」

戦場で大量の敵兵を討ち取った際、首をひとつひとつ持ち帰るのは非常に大変でした。
特に足軽が首級を腰に下げるには重すぎます。
そこで、首の代わりに耳や鼻、あるいは上唇の部分だけを切り取って持ち帰るということが行われました。
上唇には髭の剃り跡があるため、「成人男性を討った証拠」として通用したのです。
このようにして集められた耳や鼻は、塩漬けにされ、本国へ送られ、「耳鼻塚」として埋葬された例もあります。
特に豊臣秀吉の朝鮮出兵においては、大量の鼻が日本に送られ、京都に現存する**「耳塚(正式には鼻塚)」**として残っています。
まとめ
これらの風習は、単なる「野蛮さ」や「恐怖」の象徴ではなく、
戦国の世を生き抜くための合理的かつ現実的な選択だったとも言えます。
私たちが今こうして平和に生きていられるのは、かつてそうした過酷な時代を経てきた歴史があるからこそ。
残酷さの裏には、人間の「生きたい」という本能、そして「誇り」が確かにあったのです。

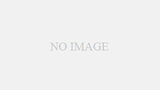

コメント